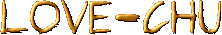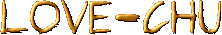目の前に広がる 炎の海。
魔物に恐れ 逃げ惑う人々。
そして 俺の腕の中で動かなくなった 大切な妹。
俺は何も出来ず ただ怒りを悲しみを吐き出すかのように泣き叫んだ。
「・・・っ!!」
その瞬間 意識は現実へと戻された。
大木を背もたれにして 睡眠をとっていたリュールは
悪夢から解放されると 長い息をつく。
また この夢か・・・。
こうした野宿でゆっくりと眠れない日には 必ずと言っていい程 見る夢。
唯一故郷と言える村 そして大切な妹。
一晩にして何もかもが消えてしまった あの日のことを。
本当に夢だったら どれだけ良かったか。 今まで 何度もそう思った。
しかし 現実とは残酷なもの。
俺は その日からトン・ソォークを倒すために旅に出た。
妹の仇をこの手で取るために。
トン・ソォークを倒すために必要な より良い武器 防具。
そして 何よりも情報を求めていろんな場所を訪ね歩いた。
旅の資金は 賞金稼ぎで手に入れていたが
最近では 千人斬りと言う肩書きのついた俺を恐れ 賞金首の輩が俺を避けてやがり
商売上がったりもいいところだった。
困難である旅が このままじゃ余計に厳しくなる。
何かてっとり早く稼げる方法を探さないとな・・・。
一度 賞金稼ぎの町に戻ってみるか。
次の日 リュールは小さな村にたどり着いた。
穏やかな空気が流れるその村は どこか懐かしい感じがした。
今日くらいは ゆっくり宿を取るかと思い 俺は前を横切る娘に声をかける。
「宿屋がどこにあるか教えてくれないか?」
「旅のお方ですか?」
「あぁ。」
「ごめんなさい。 この村には宿屋はないんです。
なにぶん山奥でこんな小さな村には 訪れる人なんか滅多にいなくって。」
「そうか。なら 仕方ないな。」
「私の家で良かったら 一晩休んでいって下さいな。」
「いや それは・・・。」
「だいぶお疲れのようですし 遠慮なさらずにどうぞ。」
「なら すまないが 一晩世話をかける。」
「たいしたおもてなしは 出来なくて申し訳ないですけど。」
「いや。 ゆっくり休めるだけでもありがたい。」
その娘の名はプー二といった。
その晩はプーニの 手料理をご馳走になり 年の頃がちょうど俺の妹と同じくらいだったせいか
プーニに妹を重ね見て 楽しいと思える時間を過ごした。
そして 誰もが寝静まり 夜も更けた頃 俺はプーニの叫び声で目を覚ました。
「キャーッ!!」
ベットの傍らに立て掛けてあった剣を手に取り 叫び声のする方へ向かった。
見るとそこには 数匹の魔物。
あのトン・ソォークの手下だ。
俺の中で 怒りの感情が湧き上がり 怒りに任せ即座に魔物を斬り捨てた。
「プーニ 大丈夫だったか?」
「は、はい。 でも 外にも魔物が・・・。 村が・・・。」
「俺に任せておけ。」
そう言って 外に飛び出した俺は おそらくきっと無我夢中だった。
守りたくても守れなった・・・ 守りきれなかった。
あの日の光景が蘇り 憎しみと怒りの全てを剣に込め 魔物をぶった斬った。
翌朝早く 誰にも気付かれぬよう村を発とうしたリュールに
朝もやの中 プーニが急いでかけて来た。
「待って リュールさん! 何も言わず 行っちゃうなんて!」
「すまない。 礼を言うのを忘れていた。」
「違う、そうじゃなくって。 お礼を言うのはこっちです。 村を守ってくれてありがとう。」
「たいしたことじゃない。 それに俺は トン・ソォークを倒す為に旅をしているからな。
当たり前のことをしたまでだ。」
「何かお礼をと思ったんだけど お金とかなくって・・・。
でも これを売ったら少しは旅の資金の足しにはなると思うので。」
そういって プーニは首にかけていたペンダントを差し出した。
それは 目利きが利かない俺でもわかるほど 高価なペンダントだった。
「それ 大事なものじゃないのか?」
「え、えぇ。おばぁちゃんの形見なんですけど。」
「なら大切にしておくんだな。 形見というのはその人の思いがこもっている。」
「でも・・・・。それじゃ 何もお礼が出来ない。」
「礼なら 先払いで頂いた。」
「え?」
「昨日の晩飯 つりが出るくらいに美味かったからな。
それに 生憎だがペンダントはもう持ち合わせている。」
優しい輝きを放つ石のペンダントを見せ 安心させるように笑うと
プーニは「本当にありがとうございました。」と深々と頭を下げた。
いつもの俺なら 謝礼としていくらか請求しただろうが
それをしなかったのは この村が故郷を感じさせる村だったからだ。
この村を守ったことが 俺にとって意味があるのかないのか それはわからない。
だが 少し救われたような気がしたのは確かだった。
何日かぶりに 賞金稼ぎの街に戻った俺は 早速 仲介所へ向かう。
「おぉ リュール 久しぶりじゃねぇか。どうだい 調子は?」
「どうもこうもねぇ。 目ぼしい賞金首はこぞって俺を避けやがる。」
「まぁ そりゃ仕方ねぇさ。 千人も斬りゃ誰しも怯えるってもんが世の常だろうよ。」
「ちっ。 迷惑な肩書きがついたもんだぜ。 おかげで金が手に入らないってんだ。」
「なるほどな。 で、今日は仕事を探しに来たってわけか。」
昔からの顔なじみである この仲介人のオヤジは
賞金首の手配がメインだが 国の傭兵やら 尋ね人やら いろんな依頼を受けている。
ようは何でも屋っていったほうが早いか。
「ま、そう言うことだ。 何かドカーンと金が入る仕事があったら回してくれ。」
「タイミングがいいな。 ついさっきでかい仕事が入ったところだ。」
「なんだ? 魔物退治か? それとも街の用心棒か?」
「いや。 ラブチュ王国の姫をさらって欲しいって依頼なんだけどな。」
そう言いながら オヤジは依頼書がまとめられているファイルをめくった。
「姫を?」
思いもしない依頼の内容に 俺は前に乗り出し その依頼書を覗き込んだ。
国同士で戦争をしているならともかく
トン・ソォーク復活で騒ぎ返ってる今の世の中
何を考えてるかわからん奴もいるもんだ。
「犯罪紛いの仕事だな。 それに ラブチュ王国か・・・。」
「どうした? 何かマズイことでもあるのか?」
「あそこの姫には えらく腕の立つ護衛隊長がついている。おそらく一筋縄でいかない。
もちろんそれ相応の依頼料なんだろうな?」
「あぁ。 でかい金額だ。 なんつっても100万ゼニーだからな。」
「100万か。 まぁ妥当だな。 それでも今の俺には十分な金額だ。」
「この仕事 受けるのかリュール?」
「受けなくてどうする。 それに、この仕事が出来るのは俺くらいだろ?」
「まぁ そうだな。 じゃあ 詳しいことは依頼者に会って聞いてくれ。」
「わかった。 早速行ってくる。」
依頼書を手渡され 時間を惜しむ暇もなく店を出ようとするリュールの背に
オヤジが声をかける。
「リュール・・・。 妹さんの仇を取るとはいえ あまり無茶をするなよ?」
「心配は無用だ。 俺様を誰だと思ってんだ?」
「わかってるさ。 けど 今の世の中何があるかわからねぇ。 死ぬんじゃないぞ。」
「ふっ。 死なないさ。」
どんな悪事に手を染めようとも トン・ソォークを倒すその日まで・・・。
決意 と言うよりも誓いを込めた手で
リュールは 妹の形見であるペンダントをぐっと握り締め 店を後にしたのだった。

|
|