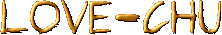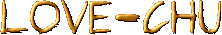うーん。 はてさて 困った。 何とかしないとなぁ。
下手に抵抗しても 歯が立ちそうにないのでリュールの後に続いて歩くサラシャは
このピンチをどうやって抜け出そうかか わりと真剣に考えてた。
このままリュールに着いていったら 依頼をした人にはぃどーぞって差し出されて
リュールは大金片手に大笑いだよねぇ。
てかさ 依頼料っていくらなんだろぅ?
これでも一国の姫なんだから 目が飛び出るほどの金額つけてもらわないとね!
って 今はそんなこと言ってる場合じゃないや。
ん? でも待ってよ。
ここは目には目ン玉 歯には歯ン玉。
依頼返しで断ち切るっていう手はどう?
サ 「ねぇ リュール。 依頼料っていくらなの?」
リ 「100万ゼニーだ。 俺の旅の資金には十分すぎるほどの金額だ。」
サ 「じゃあさ その3倍出すから私の依頼を受けてって言ったら聞いてくれる?」
リ 「3倍!? 300万ゼニーだぞ!?」
サ 「うん。そんくらい軽い軽い♪ 私がラブチュ王国の姫だってことは知ってるんでしょう?
今ならラブチュ地ビールの呑み放題券も付いてくるよ。」
リ 「・・・・・喰えないお姫さんだな。」
サ 「地獄の沙汰も金次第って言うしね。 ミイラ取りがミイラになったっていいじゃない♪」
リ 「ふん。 まぁいいだろう。」
サ 「交渉成立ね!」
リ 「で 依頼とは?」
サ 「私をドラゴ王国まで連れてって。 みんなもドラゴ王国に向かってるだろうしね。」
サラシャの作戦は見事成功した。
こうして二人はドラゴ王国へ向かうことになった。
リュールの話によると ここからドラゴ王国までそう遠くはないらしい。
とりあえず難を逃れたサラシャは おやつでも食べようとチョコレートを取り出した。
サ 「チョコレート 食べる?」
リ 「甘いものは嫌いだ。」
サ 「後で欲しいって言ってもあげないよ?」
リ 「言うかっ!!」
サ 「美味しいのに〜。」
ロクスがいないので おやつ食べ放題のサラシャは
ここぞとばかりに ポイポイッとチョコを口に放り込む。
サ 「さっき モグモグ 旅の資金って言ってたよね? モグモグ」
リ 「あぁ 言ったな。 てか、食べるか喋るかどっちかにしろ。」
サ 「まぁまぁ 小さいことはいいじゃない。 で、何の目的で旅してんの?」
リ 「トン・ソォークを倒すためだ。」
サ 「え!? トン・ソォークを倒すって・・・ ねぇ、もしかして赤い石持ってない?」
リ 「赤い石? これのことか?」
リュールが取り出したペンダントの先に付いているのは 間違いなく赤の輝勇石。
まさかこんな形で見つかるとは・・・
ビックらこいたサラシャは 驚き半分喜び半分で心臓がバックンバックンした。
サ 「私たち赤の輝勇石を探してて・・・。」
リ 「輝勇石?」
サ 「うん。 この石は 闘志の意味を持つ輝勇石。」
そう言ってサラシャが 輝勇石に触れようとすると
思いっきしリュールに手を払われた。
サ 「な、何よぅ いきなり!!」
リ 「この石に触るな。 輝勇石だか何だか知らないが これは・・・
この石は妹のたった一つの形見だ・・・。」
輝勇石をグッと握り締め リュールは怒りにも似た表情を浮かべる。
サ 「形見? 妹さん・・・ 亡くなったの?」
リ 「・・・あぁ。 トン・ソォークの手下に殺された。」
リュールは幼い頃に両親を亡くし 妹と二人で暮らしていた。
幼い兄妹に世間は冷たく
働こうとしても 子供だからという理由で雇ってもらず
貧しい生活が続く日々。
そんな中 てっとり早くお金を稼ぐ方法としてリュールは賞金稼ぎの道を選んだ。
必死で剣の扱いを覚え 高値の賞金首を狙い
名の知れた賞金稼ぎになるまで数年。
リュールの稼ぎで お金に苦労することはなくなり
二人は生まれた街を出て 小さな村へと移り住んだ。
世間一般では賞金稼ぎと聞くと 悪いイメージを持たれることが多いが
その村では 皆が優しく兄妹を受け入れてくれて 幸せな日が続いてた。
あの日までは・・・・
妹 「今日はお兄ちゃんの誕生日だから 早く帰ってきてね。ご馳走作って待ってるから。」
リ 「わかった。 楽しみにしてるよ。」
しかし その日に限って仕事が手こずり帰宅時間が遅れてしまった。
急いで妹が待つ家に戻るリュール。
しかし リュールを待っていたのは無残な村の姿だった。
リ 「こ・・・ れは・・・」
真っ赤に燃える村。 一瞬何が起こったのか理解出来なかった。
無我無心に走り 今にも崩れそうな家のドアを開けると
炎の中で横たわる妹がいた。
妹 「お兄・・・ちゃん。」
消えそうな声で自分を呼ぶ妹に駆け寄り抱き起こすと
妹はリュールの顔を見て安心したように微笑む。
妹 「これね・・・ 川で見つけたんだけど
凄く綺麗だったから お兄ちゃんのプレゼントにって ペンタントにしてみたの。
良かった・・・ 渡すことができ・・て・・・」
リ 「もう喋るなっ!」
妹 「誕生日・・・ おめで・・・と・・う・・・」
そして 妹はそのまま静かに息を引き取った。
妹からプレゼント。 炎よりも赤く輝く赤い石のペンダント。
それをグッと握り締めるリュールの手から 赤い血が滴る。
俺がもう少し早く帰っていれば こんなことには・・・。
溢れる怒りと悲しみの中 リュールは生まれて初めて声を出して泣いた。
サ 「だからトン・ソォークを倒す旅に出た。
そして それがその時のペンダントが それなんだね・・・。」
リ 「あぁ そうだ。 俺が手にした時からこの石は輝きを放った。
俺は 妹の魂がこれに宿っていると信じてる。」
サ 「ごめん。 気安く触ろうとして。」
リ 「ふん。 わかりゃいいんだよ。」
ちょっとこの人悪い人かもと思ってたリュールは
実は辛く悲しい過去を背負って生きている人だった。
胸に秘めた怒りと悲しみは きっと計り知れないないものだろう。
罪のない人たちが あまりにも早く散ってゆく。
こんな世の中にした全ての根源は あのトン・ソォーク。
リュールと共に闘いたい。
サラシャは目に見えぬものを背負ったリュールの背中を見てそう思った。
 
|
|