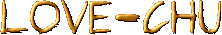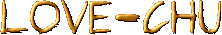ドラゴ王国へ向かうサラシャとリュール。
チョコレートを全て食べつくしたサラシャは
あとでロクスに怒られちゃうなぁ〜などと思いながらも 先ほどから考えていたコトを口に出した。
サ 「あのね リュール。 私たちと一緒に来ない?」
リ 「依頼の次は勧誘かよ?」
足を止めずに気のない口調でそう答えるリュールにサラシャは続ける。
サ 「う〜ん。勧誘ってわけじゃないけど。言い方を変えると私たちと一緒に来るッ!」
リ 「って、決定かよッ!!」
サ 「決定というか決意だよ。リュール自身の覚悟が必要なの。
リュールは赤の輝勇石に選ばれた戦士だから。」
リ 「そういやさっきも輝勇石がどーこー言ってたな。何のことなんだ?」
煙草に火をつけて訊ねるリュールにサラシャは一つ一つ確かめるように説明をしていった。
世界に散らばる6つの輝勇石。そして虹色の剣。
それらはトン・ソォークを倒すための唯一の光であること。
そして青の輝勇石タトゥミのこと 緑の輝勇石ヒヨのこと。
今まで歩んできた全てをリュールに話した。
サ 「私ね 今までは旅に出ることや闘うことは本人の意思に任せてきたの。
でもリュールはすでに私たちと同じ道を歩いてる。だから一緒に来て。」
リ 「・・・・断る。 俺に仲間は必要ない。
俺は今まで何事も一人でやってきた。これからも俺は俺のスタイルでやらせてもらう。
あんた達はあんた達でやればいい。」
サ 「一人じゃトン・ソォークを倒すことは出来ないんだよ?」
リ 「そんなのはやってみなくてはわからないだろうが!
俺は自分一人の力で奴を倒したいんだ。」
サ 「何よ! 馬鹿みたいにかっこつけて!」
リ 「あ? んだと こら! もっぺん言ってみろ!」
サ 「何度でも言ってやるわ。 バーカバーカぉ馬鹿のかっこつけ!
自分一人の力で倒したい? そんなの自己満足に過ぎないじゃないの!」
リ 「違うっ! 俺は妹の仇をッ!!」
サ 「本当にそう思ってるのなら・・・・
今まで貫いてきたものを捨ててまでも 私たちと一緒に来るはずよ。」
リ 「・・・っ。」
サ 「力を合わせればトン・ソォークを倒せるかも知れないんだよ?
妹さんだってそれを願ってるはず。
だって・・・ その輝勇石は妹さんから託されたものなんだから・・・。」
リ 「妹も・・・・・・」
リュールは再び輝勇石を手に取り見つめた。
何より愛しかった妹を見つめるかのように。
一人では無理?
頭の片隅でそう思ったこともあった。
しかし 今まで自分が積み重ねてきたもの
そしてトン・ソォークへの怒りを奮い立たせ
そんな考えは打ち消してきた。
誰にも邪魔はさせない。
おまえの仇は 俺が取る。俺だけの力で奴を倒す。
例えその結果 俺が死ぬことになっても構わない。
この考えは 間違っているのか・・・・
お兄ちゃん。 迷ってるの?
私はいつもお兄ちゃんの味方だから。
でも あまり一人で頑張りすぎないで・・・。
お兄ちゃんが本当に今やるべきことは何なのか 考えて・・・。
握り締めた輝勇石から そう聞こえた気がした。
それとリンクするようにサラシャの声がリュールに届く。
サ 「リュールにしか出来ないことがあるんだよ。それをちゃんと考えて。」
リ 「ふっ。」
いつのまにか消えていた煙草を吐き捨て リュールはうつむきながら笑みを浮かべる。
そして 何かが吹っ切れたように空を見上げ 息を吐くようにサラシャに言った。
リ 「わかった。 一緒に行こう。」
サ 「そうこなくっちゃ!」
リ 「だけど一つ言っておく。 俺は仲間とかそういうのには興味がない。
ただ妹から託されたこの輝勇石の使命を果たすために行くだけだ。」
サ 「うん。それで十分だよ。」
リ 「しかし まぁ あんたに丸め込まれるとはな。一流の賞金稼ぎの名が泣くぜ。」
サ 「丸め込むって失礼ね。 諭すって言って頂戴。
それにね私にはサラシャという可愛い名前があるんです−!」
リ 「わかったわかった。あ、それから300万ゼニーは後でキッチリ頂くからな。」
サ 「契約は契約だものね。 そのかわりロクスがいない分しっかり護衛して
ちゃんとドラゴ王国まで連れてってね。」
リ 「ふん。 お安い御用だ サラシャ。」
姫と賞金稼ぎ。
そんな二人の間に 共にトン・ソォークを倒すという一つの志が出来た。
ドラゴ王国―――――――
マ 「ここは・・・? うっ・・・」
ひんやりとした硬い感触に目を覚ますと同時に また激しい頭痛がマオンを襲う。
痛みをこらえマオンは体を起こして 辺りを見回した。
薄暗く湿った空気。
まだぼやける視界の中に見える鉄格子。
ここはもう何年も使われることのなかった 城の地下牢。
なぜ 自分がこんなところに?
確か黒い霧が王国を包んで・・・・
? 「もう起きてしまったか。」
記憶が途切れる前のことを思い出すマオンに
鉄格子の向こうから 話しかける者がいた。
マ 「そこにいるのは 誰!?」
? 「トン・ソォーク様に仕える参謀の一人。我が名はトン・カチ。」
マ 「私を捕らえてどうする気? つーか、ここから出せ このやろう!」
カチ「威勢のいい姫さんだブ。 よほど精神が強いんだブ。
黒の霧を浴びても魔物にならないとは。」
マ 「何よそれ? どういうこと? ・・・・・まさかあの霧。」
カチ「察しの通りだブ。 普通の人間なら霧を浴びれば身体に闇が巣食って魔物になるブ。
見た目は人間でも中身は魔物。 この国はトン・ソォーク様の手に落ちたんだブ!」
マ 「そ、そんな・・・」
カチ「悲しむことはない。お前もすぐに仲間入りだブ。」
そう言うとトン・カチは気味悪い笑みを浮かべて 香炉を取り出した。
ようやく視界がはっきりとしてきたマオンはそれを見て 危険信号をすぐに察知した。
が 気づいた時には すでに遅かった。
そこから溢れでる黒い煙。 それは王国を覆った黒い霧と同じもの。
瞬く間にマオンを取り巻き マオンは膝から崩れ落ちた。
倒れまいと鉄格子を握る手の力も だんだんと弱くなっていく。
ついには 冷たい床に横たわってしまった。
薄れゆく意識の中で 遠くトン・カチの声が聞こえる。
カチ「魔物になったお前には あいつらを討つ使命を与えてやるブ。」
ここで意識を失くすわけにはいかない。
サラシャに伝えなければいけないことがある。
マオンは 身体を蝕む闇と闘いながら
護身用に持っていたナイフで 自分の手のひらを切りつけた。
流れ出す血と共に鋭い痛みが走り その痛みに耐えながら意識を手放すまいとしていた。
サラシャ早く・・・ 私の意識があるうちに・・・
 
|
|