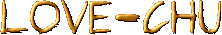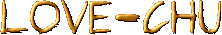サラシャはテントの隅で 荷物の整理をしていた。
だが その手はさっきから止まったままだ。
一人の空間は 昨日の出来事を嫌と言うほど思い出させ 後悔の念がサラシャを襲い
やがてそれは悲しみへと変わり 涙がこぼれた。
そんなサラシャに テントに入ってきたヒヨが静かに話しかけた。
ヒ 「サラシャ。 ちょっといいかな?」
サ 「な、なに?」
ヒ 「人知れず涙するのは とても辛いことだよね」
サ 「私 泣いてなんかッ・・・」
ハッと我に返り 急いで涙を拭ったサラシャだったが
赤くなったその目は ヒヨを誤魔化すことは出来なかった。
ヒ 「サラシャ。 ここでは 姫でいる必要なんてない。
だから 我慢して感情を一人でしまい込まないでほしい。
自分だけに負担をかけちゃいけないよ。
サラシャの悲しみは僕達みんなで受け止める。
何も気を遣うことなんてない。
思ってることをそのままぶつけてくれても構わないんだ。 仲間だろ 僕たち」
サ 「ヒヨ・・・・・」
ヒ 「それとも 僕達じゃ頼りない? そりゃ ロクスに比べたら・・・」
サ 「そんなことない。 頼りなくなんかない! みんながいてくれて本当に心強いわ。
だけど・・・ だけどね」
ヒヨの言葉に感情を露にしたサラシャが 手で顔を覆うようにして大粒の涙を流した。
サ 「どうして みんな 私を責めないの?」
ヒ 「サラシャを責める? どうして?」
サ 「だって 全部私のせいじゃない。 吊り橋を渡る前 遠回りしようと言ったロクスに対して
私は ただ自分の感情だけで反対の意見を言ったの。
本当なら回避出来た事態だったのに 私の馬鹿な意地が
みんなを危険な目にあわせ ロクスだって・・・。 いっそ私が落ちれば良かった!」
ヒ 「あの時の判断が正しかったとは言えないかも知れないけど
過ぎたことは仕方がないことだろ? それに誰もそんなこと思っちゃいない。
サラシャもさっき自分で言ったじゃないか。今 自分に出来ることをするって」
心に抱いていた不安を取り除くヒヨの言葉に サラシャは顔を上げゆっくりと頷く。
そして ヒヨはもう一つの不安に触れた。
ヒ 「ロクスなら大丈夫さ。 以前ロクスはサラシャを守って死んだも同然の傷を負ったって・・・
でも 信じられない回復を遂げたって・・・。
だから 今回だって 信じられない奇跡を起こすさ」
サ 「・・・うん、そうだよね。 ロクスは死なない。 ありがとうヒヨ」
ヒヨのおかげで 胸のつかえが取れたサラシャには いつもの表情が戻り
そして 遠い昔の約束を思い出した。
谷底に落ちたロクスは 濁流に流され やがて川岸に打ち上げられた。
傷だらけになったその体は 何度も岸壁に打ち付けられたことを物語っている。
体温も低下し 思うように体が動かず ただ消えそうな息を保っているだけの状態だった。
指先を動かすことも出来ないくらいに重みを感じ 視界もぼやけ 意識が朦朧とする。
痛みという感覚など もうとっくに通り越していた。
俺は このままここで果てるのか・・・。
この感覚
いつだったかも 同じようなことが・・・・・・。
まぶたを閉じると 薄れゆく意識の中で 遠い記憶が蘇った。
あれは 俺がまだ護衛隊長に就任して間もない頃・・・
王国騎士において 王族専任の護衛隊長になることほど 名誉なことはない。
だが蓋を開けてみれば 護衛隊長とは名ばかりで
子守り役の日々が続く。
そんな毎日に 自分の存在は何なのかと疑問に思うことも多々あった。
王国への忠誠心を掲げながらも
城を抜け出したり 木登りをしたり 泥だらけになるまで走り回ったりと
とても姫だとは思えないサラシャの行動に 正直俺はうんざりもしていた。
そんなある日 いつもの我侭から 野生の動物が見たいからと言って
サラシャに付いて 王国より少し離れた森へ出かけた。
丸一日森で過ごし 日も傾きかけた頃 ことは起こった。
ロ 「姫様。そろそろ夕食の時間ですし 城に戻らないと」
サ 「えー。夕食なんて遅れても構わないからもっと遊びたい」
ロ 「しかし 姫様の姿がないと皆が心配します」
サ 「厳しいなぁ ロクスってば。 つまんないの」
ロ 「また明日来たらいいじゃないですか」
サ 「そだね んじゃ明日もよろしく。それよりもロクス」
ロ 「はい?」
サ 「その 姫様っていうの 何だか堅苦しくって嫌なの。サラシャと呼んでくれない?」
ロ 「そうはいきません。俺は姫様をお守りする身分 名前で呼ぶなど以ての外です」
サ 「それが嫌なんだってば。それにその敬語もなんとかならない?
私 ロクスとは対等でありたいのよ」
ロ 「いくら姫様の頼みでも それだけは聞けません。 さぁ城に戻りましょう」
対等であれるはずがない。
王族をファーストネームで呼ぶのが どれほどのことかわかっていない。
俺は もっと姫としての自覚を持つべきだと苛立ちさえ感じ
足早に森を抜けようとすると 視界の隅で草むらが動くのを確認した。
サ 「あ! 何かいる♪」
ロ 「危険な動物かも! 不用意に近づいては・・・!」
俺から離れ一目散にその場へ駆け寄ったサラシャの前に現れたのは
危険な動物よりも もっと質の悪いものだった。
「誰かと思えば ラブチュ王国の姫さんじゃないか」
「こんな所で出会えるとは 俺たちゃついてるな」
サ 「えっ!? 何よあなた達! 離してっ!!」
現れた連中は怪しく笑い サラシャを捕らえた。
他にも続々と仲間が現れ その数15人。
ロ 「姫様を放せ」
俺は剣を抜き構え 連中を鋭く睨みつけた。
「放せてと言われて放す程 俺たちは物分りがよくなくてな」
「こんなおいしい儲け話 他にはねぇからなぁ」
「そうそう。 こんな森の奥に 子供二人でいるほうが悪いぜ」
ロ 「子供ではなく 護衛隊長だ。 俺を甘く見るなよ」
サ 「ロクス。 気をつけて この人たち・・・」
怯えながらそう言うサラシャに 俺は無言で頷く。
以前 騎士団会議でも議題に挙がっていた山賊だ。
「お前のうような小僧が護衛隊長とは お笑い種だぜ」
「姫を無事に帰して欲しかったら 金を用意して来い」
「そうだな。500万ゼニーでどうだ?」
ロ 「断る! 姫様に傷一つ付けてみろ。 ただでは済まさないからな」
「ふん。 威勢がいいのも考えものだぜ」
山賊は サラシャの頬にあてがったナイフの刃先を なぞるようにゆっくりと下にひいた。
すると その傷跡を示すようにサラシャの頬を真っ赤な血が滴る。
サ 「・・・ッ!!」
ロ 「ひ、姫ッ!」
「さぁ どうするよ?」
ロ 「貴様らっ・・・。 その罪 死で償ってもらう」
怒りで体中の血が沸きかえった。
怒りで声が震えたのも 初めてだった。
俺は 剣を握る手に更に力を込め 容赦なく斬りかかる。
ロ 「覚悟しろ!」
「覚悟するのは てめぇのほうだ。 皆 殺っちまえ!」
剣の腕には 自信があった。
王国騎士団の誰よりも優れていると・・・。
だからこそ 若くして護衛隊長にも任命された。
だが その若さゆえ この時の俺には実戦の経験が乏しかった。
多人数相手に ただ一人で闘うことなど なおさらだった。
山賊の何人かは斬ったものの 隙をつかれ頭上に剣が振りかざされ
とっさに反応したが 避け切れず額を深く斬り付けられた。
痛みより先に熱を感じ 流れ出した血で視界が赤に染まる。
一瞬よろめき体勢を立て直すと 次は横腹を突き刺さる痛みに襲われた。
そして 続けて背中に・・・。
ロ 「うぐっ・・・」
吐き出す血の味 吹きだす血の音 赤く染まる視界
充満する血の匂い そして脈打つ体。
五感の全てが血で埋め尽くされたその時 俺が感じたのは
死への恐怖ではなく 護衛隊長としての使命感だった。
そして 最後とも言える力を振りしぼり
自分の体をかえりみず 残りの山賊を斬り倒した。
サ 「ロクスッ!」
ロ 「姫様・・・。 ご無事でなりよ・・り・・・です」
サラシャの無事を確認すると 一気に力が抜けその場に倒れこんだ。
もう思うように体が動かない。
俺は このままここで果てるのか・・・。
サ 「しっかりして!」
ロ 「姫様をお守りして 死ねるなら本望です・・・」
その言葉に嘘偽りはなかった。
王国への忠誠心。 命をかけてお守りすると
国王専任護衛隊長である父君に 小さな頃から何度もそう言われていた俺だからこそ
自然に出た言葉だった。
サ 「何を言ってるの! あなたは私の護衛隊長なのよ?
ロクスが死んだら 私は誰に命を預けたらいいの!?
私を置いて死ねるものなら 死んでごらんなさいよ!」
この時 初めて 命をかけて守る本当の意味を知った。
自分の命ではなく 姫の命をかけているということを。
護衛隊長とは絶大な信頼を受ける 無二の存在。
俺の死は すなわち姫の死に繋がる・・・。
その後 まだ城に戻らない姫を探しにきた騎士団に救護され
約半年かけて おれは奇跡的な回復を遂げた。
その間 一度たりとも姿を見せなかったサラシャは 試練の間に閉じこもり
治癒能力を身に付けていた。
サ 「この先ロクスが剣で戦い傷つくことがあったら 私が治してあげるからね。
これからは私も守られてるばかりじゃないんだから。 ね、これで対等でしょ?」
幼くして治癒能力を会得するのは どれだけの苦難を要したことか・・・。
対等でありたいと願うサラシャに 俺は敬意を払ってその名を呼ぶ。
ロ 「そうだな・・・。 サラシャ」
サ 「うむ。それで良し! 余は満足じゃ♪
あ、そうだ。 その額の傷治してあげるよ」
ロ 「いや。この傷はこのままでいい」
サ 「どうして?」
ロ 「自分への戒めとして 刻み込んでおきたい」
サ 「そう? ロクスがそう言うのなら 仕方ないけど」
ロ 「サラシャ」
サ 「ん?」
ロ 「この傷にかけて誓う。 二度と危険な目に合わせないと。
そして 死なないと約束する」
サ 「うん! もちろんだよ!」
あの日誓った約束。
そうだ・・・・。
だから 俺は死ねない!!
ロクスは手放しそうだった意識を再び掴み 力強く瞳を開いた。
 
|
|